※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。
前回の癇癪対応(2歳編)に引き続き、今回は癇癪対応(3歳編)です。
3歳になると発語も増え、言語理解もできることが増えてきました。また、外出先が広がったり幼稚園入園でお友達との交流も増えたりと娘の世界がお家からお外に広がっていった時期でもあります。
娘の癇癪度合いや実際に取り組んで効果的だったこと、その詳細なども併せてお伝えします。
癇癪で悩む親御さんが少しでも楽になりますように・・・・!!
※子供の癇癪の度合いは個人差がありますので、下記のことをすれば誰でも癇癪が治まるといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。
癇癪対応3歳編
娘の癇癪度合い・スイッチの入り方

2歳の頃の娘は「自分が嫌なこと」「やりたかったのに出来なかった」など自分の快・不快を基本とした癇癪が多かったです。
まだ発語も少なく言語理解も乏しかったため、とにかく「癇癪の機会を作らせない」「癇癪ポイントが来る前の対応で逆に褒めるポイントを作る」のやり方で癇癪対応をしていました。
3歳になると発語も増え、言語理解も伸びてきました。そのため今までの様に「物(ご褒美)を利用して対応する」やり方から少しづつ「言葉で伝える・ご褒美以外のもので対応する」ことを試していきました。
3歳の頃の娘の癇癪

この頃の私は 発語あり(単語600語ほど)・自分の嫌な主張が言葉でできる・約束が理解できる・ほんのり手がつなげる・まだ人より物に興味ある 状態だったよ!
もっと詳しく発達状態を見たい方はこちらの記事からどうぞ。
◉癇癪の内容
- 朝の登園しぶりがほぼ毎日あり、玄関を出た瞬間「幼稚園やだ、だめ、行かないよー!」と言って泣きながら動かなくなるためバス停まで鮮魚ピチピチ抱っこモードでダッシュで送りに行く
- お風呂上がりの着替えを拒否。裸のまま脱衣所で泣き喚く。リビングまで移動させようと抱っこしてもすり抜けてしまう。
- 夜寝る時間になって「寝るよ」と声がけをすると「眠くないからまだ遊びたい!」といい泣いてソファーにしがみつく(寝室に行きたくないため)
- お風呂に入る際にバスボールを使いたい、使わないなら入らないと泣き喚き「ママ嫌い!!」といい私を押したり自分の手を口に入れようとしたりする(若干パニック)
- 幼稚園での癇癪(お外遊びからお部屋に入るときに切り替えができず泣き叫ぶ)
- 療育中苦手な課題が出てきた時に「やりたくない!」と泣き崩れて床に突っ伏し、療育終了後も「帰らない!」と自転車に乗車拒否。暴れて危ないため先生に一緒に自転車置き場まで来てもらう
- 病院の待合室で待てない、不安感で泣きわめいてしまう
※病院に慣れるまでの取り組みはこちら
など。
この時期は2歳の頃のように自分が「やりたい遊びが出来ない!」から癇癪をすることもありましたが、「うまく出来ない」「苦手だからやりたくない」「病院の待合室で泣く」のような少し見通しが通せる様になったからこその癇癪も出てくる様になりました。
また、「あの子と遊びたいのに遊べない!(明らかに年齢が離れていたり、相手が乗り気じゃなく私が気を遣って離そうとした)」などの他人への興味が出てきた故の癇癪もありました。
ただ外出先での床に突っ伏してする癇癪や、人目が多くある場所での大癇癪などは減ってきた為、若干場所を選んで癇癪をしてるような感じもありました。
※幼稚園の年少時代の様子がわかる記事はこちら
3歳の頃に行った癇癪対応

外出する前に「お約束」を伝える
癇癪って外出時にされてしまうと周りの目もあって焦って「やめなさい!」「泣かない!」などと怒ってしまうこともありますよね。
お家なら多少泣き叫んで床に突っ伏しても安全も確保されている分対応に集中できたりもするのですが、お外だとなかなかお家のように落ち着いて対応できなかったりします。
なので、外出する予定がある場合は以下の様にお約束を決めて前もって娘に伝えることを徹底していました。
スーパーの場合

スーパーでは
①走りません ②泣きません ③イヤイヤしません ④手を繋ぎます ⑤おもちゃは買いません

このお約束を守ってお買い物ができたら、200円より小さいお菓子をひとつだけご褒美に買ってあげるよ。どうかな?出来そう?
公共機関に乗る場合

電車(バス)に乗るときは
①走りません ②泣きません ③席に座れなくてもイヤイヤしません ④手を繋ぎます

このお約束を守って電車に乗れたら、お出かけ先で31アイス一緒に食べよう!どうかな?出来そう?
児童館などに行く場合

児童館に行くときは
①館内は歩きます ②他のお友達には優しくする ③泣きません ④帰る時にママと一緒にお片付けする

このお約束を守れるなら、おもちゃがいっぱいの楽しいところに連れて行くよ!どうかな?できる?
こんな感じで、お約束→ご褒美の提示→可能か聞くの順番に娘に伝えていました。
これは本当に毎回毎回一度も欠かさず伝えています。
もちろん今現在(2025年1月もうすぐ5歳時点)でも伝えています。
お約束をするタイミング
家を出る前、お店に着いた時、入店して通路を歩いている時の3回です。
また、約束を守らずに度を越した癇癪などした場合は「何も買わずに帰る」を実行しました。
3歳になってすぐの時期は「やっぱりおもちゃが欲しい!靴下が欲しい!」などとたまに癇癪をすることがあったのでその場合は「初めに言った通りに帰るよ」と即帰宅をしていました。
3歳半頃になって、上記のような癇癪を起こしそうになった時は
「ここでイヤイヤをするとご褒美はもらえないけど、おもちゃを返せばお菓子は買ってあげられるよ、どうする?」
と即帰宅はでは無く、娘に「どうするか?」を聞きながら買い物をするようになりました。
娘としても何も買ってもらえずに帰宅よりはお菓子を買ってもらう方が得なので「おやくそく守る!」と考え直すことが多くなり、大分癇癪も減りました。
※このやり方はABAとABC分析を参考にしています。
ABAとABC分析の詳細について書いてる記事はこちらです。

↑魔法の言葉かけにも詳しく記載されてます〜
出来ないことは出来ないと伝える
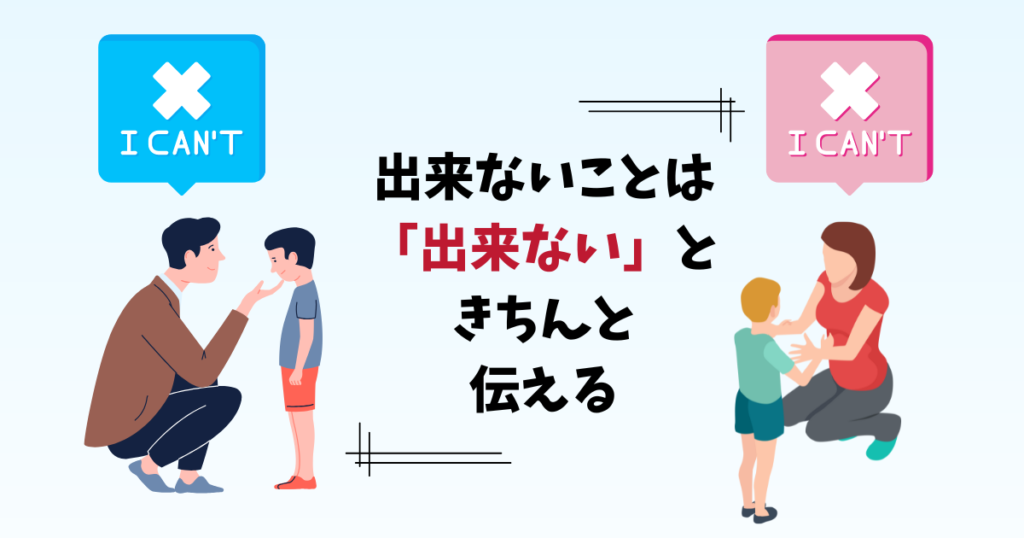
本当なら子供の希望にできるだけ沿って対応してあげたいけど、出来ない時って絶対にありますよね。
うちの場合は、
「着替えしたくない!パジャマで幼稚園いく!」
「ママも(幼稚園の)バス乗って!!」
「(夜10時過ぎても)眠くない!まだ遊ぶ!起きる!」
などでした。
厳密に言えば、パジャマで行っても着替えさせてもらえるだろうし10時になっても寝かせなくても大丈夫っちゃ大丈夫ですが、「それでいいんだ」と誤学習された後に「あれは特別だったけど今日はダメ」と訂正するのはあまり良くないかなと思ってます。
なので、誤学習させたくない内容or現実的に出来ない内容 に対する癇癪については、「出来ないことは出来ないよ」とキッパリと伝えてどれだけ癇癪されても折れずに対応しました。
ただ、言語理解ができる様になったとは言え、「〜だからできないよ」という理由づけをした上で伝えてもすぐに「わかった」とはならない時ももちろんあります。
そんな時は娘も譲らないため床を転がったり泣き叫んだりしてしまいます。外でされると対応が出来ない場合もあるため、「出来ない」という旨を伝える時は外ではなくお家の中で行いました。
お家の中であれば安全を確保した上でならある程度泣いたり暴れたりしてもこちらも折れずに対応することができます。
長い時間癇癪が続いてしまうと「わかったよ、じゃあそうするから泣き止んでよ」や「テレビ見る?お菓子食べる?」とその場を収めるために便利グッズを使ったり諦めたりしたくなってしまいますが、癇癪を元に誤学習してしまうと子供が「癇癪は便利だ!もっと使おう!」という考えをもってしまうかもしれません。
それは本当に避けたいことだと思うので、安全面だけは配慮しつつ一度決めたことは折れずに対応しましょう・・・!!(心は折れそうになりますが・・)
そして、ひとしきり癇癪して子供の気持ちが落ち着いてきたところで、

娘ちゃん 少しお話ししてもいいかな?

・・・・・(泣き疲れて不服の表情)

娘ちゃんは○○がして欲しかった(したかった)んだよね、叶えてあげられなくてごめんね、でも幼稚園は制服に着替えてから登園するっていうルールがあるんだ。
娘ちゃんがパジャマで行って、それを見たお友達が「私もパジャマで行きたいな!」って皆が言い出したら先生は嬉しい?それとも困るかな?どう思う?

・・・・こまる・・・

そうだよね、皆がパジャマで来ちゃったら先生困っちゃうよね。でもきちんと制服で来てくれたら先生も嬉しいし、朝の会も早くできて娘ちゃんの好きな遊びもその分沢山できるかもしれない。
だから幼稚園の日はお着替え頑張ってくれたらママも嬉しいな。もし難しかったらいくらでも手伝うし、それでも嫌だなって時は靴下だけ自分で履いて、あとはママにお任せでもいいよ、どうかな?

・・・・わかった、じゃあお着替えする

ありがとう!!わかってくれてすごく嬉しい!!
こんな風にうまくいく時もあれば、うまく行かない時もあります。
でも大体は上記のように
- 気持ちが落ち着いているか確認(「話してもいい?」の問いかけに「うん」や無言状態だったら次も話始めますが、話しかけた状態でまたグズグズしたら「また後で話すね」とその場を離れます)
- 子供がやりたかったことを叶えてあげられないことに対して謝る
- こういう理由で「できない」と言ったんだよと理由を伝える
- 子供がやりたかったことをそのままやらせたらどんなことが起きるのかな?と想像させる
- もし子供が納得してくれたら「じゃあこういう風にしてくれたら嬉しいな」の提案をする
※納得しない場合は「そうだよね、嫌なんだよね」と一旦気持ちを受け止め直す - 提案に乗ってくれたらめちゃくちゃ褒める
の一連をやっていました。
正直「幼稚園のルール云々」を伝えても納得はできない部分が多いだろうなと思いながらも、園での集団生活はルールだらけということもあり、「自分の気持ちがいつも最優先されるわけではない」という事についても触れておこうと思ったため伝える事にしていました。
むしろ園では一人にこんなに時間をかけて諭すことも中々できないだろうという思いもあり、お家で癇癪が起きた時はルールや守らなければいけないことについて話す機会と捉えて伝えていました。
癇癪の見本を親が見せ危険性を伝える

お外での癇癪って、場合によってはめちゃくちゃ危ないですよね。
道路のそばでやられたらいつ車が来るかわからないし
地面が固いコンクリートなら突っ伏した時に頭や顔を怪我するかもしれない
腕を引っ張ったり無理に抱き抱えようとしたら腕が抜けたり指が折れたりするかもしれない
なので「もしかしたら今日外で癇癪起きるかもしれない」と思う要素があるとき(病院に行く、新しい玩具屋さんに行く、自分の用事だけ済ませるために外出する、特に子供にメリットの無いお出かけをする など)は、
「お外で嫌なことがあったら、体でイヤイヤせずに言葉で伝えてほしい」
「なぜかというとお外でイヤイヤするのはすごく危ないから」
「今から見本見せるから見ててね」
と上記の内容を伝えて、外で癇癪したらどうなるかの見本を見せていました。
- ゴロゴロ転がって手足をバタバタさせ、癇癪を表現する(泣きまねもする)
- 激しくソファやおもちゃなどの障害物に自分からぶつかりに行く
- 「うっ、痛い!お外でゴロゴロしたから地面にぶつかって歯が折れちゃったよ〜!手足も擦りむいてヒリヒリして痛いよ〜!」
- 「あ!地面にゴロゴロしてたら前から車が来てるよ!車にぶつかったら大変だよ!危ない!でも痛くて立てないよ〜!」
そして、見本を見せたら

今の見てさ、お外でイヤイヤするのって危ない?危なくない?

危ない

そうだよね、よくわかったね!すごく危ないし、娘ちゃんがすごく痛くて嫌な思いをするかもしれないよね!
だから、お外で嫌な気持ちになったら体でイヤイヤするんじゃなくて、言葉で「嫌!」ってママに伝えてくれる?そしたらママもお話し聞けるからさ!
※お出かけ自体に恐怖心がつきそうなお子様の場合はやらないでください
という感じで「嫌な時は体じゃなく言葉で伝えて!」+「外での癇癪はあなたが痛い思いをする」ことを強調しながら伝えていました。
それでもお外で「あっ やばい癇癪起きそう」となった時は「娘ちゃん、嫌な時は嫌って言っていいよ、嫌な気持ちママに教えて?」と言葉で伝えることを促し続けたら娘も思い出したかのように言葉で「○○が良かった」「嫌だった」などと教えてくれるようになりました。
それでも癇癪が起きてしまったら?

安全の確保+感情的にならない+他害が出ないように配慮する
上記1〜3の対応はほとんどが「癇癪を回避するための先回り」的対応です。
それは実際に癇癪が起きてしまってからの対応がものすごく難しいからです・・・。
うちの娘は癇癪の頻度はそこまで高くはありませんでしたが、一度癇癪になってしまうと本当に周りからの声がけが聞こえなくなるような感じで軽いパニック状態になり、気持ちの切り替えが中々できませんでした。
特に外で癇癪が出てしまうと泣き叫ぶ声も大きいし床に転がったり「手を離せ!」と乱暴な言葉遣いが出たりしていました。
3歳を過ぎると体も大きくなりますし抱き抱えることも難しくなりますよね。
なのでとりあえず、
最低限の安全を確保し、(これがまた難しいですが)他害が出ないように、可能であれば背後から手を押さえて引っ掻きや噛みつきが出ないようにする、落ち着くまで変に言葉がけはしないけど言いなりにはならない
を意識して対応していました。
興奮している時に他害が出てしまうと親が怯むのでそれもまた誤学習につながる可能性が多いと療育の先生に教わってからは絶対に他害だけはさせないように気をつけていました。
ちなみにお家で癇癪が出た場合は手を押さえずに自分がその場から離れるだけにしていました。(こちらも最低限の安全は確保しながら)
そして泣き叫ぶ声が無くなったり抵抗する力が弱まってきて「そろそろ話が通じる頃かな?」と思ったら、

嫌だったね、何が嫌だったか教えてくれる?
と話しかけて、
「好きなようにさせてあげられなかったのはごめんね、でも、外でのイヤイヤは危ないからママ次はして欲しくないな、イヤイヤをされても娘ちゃんの思い通りにならない事もあるんだよ。逆に言葉で伝えてくれたら叶えてあげられることもあるかもしれない。だから今度は言葉で伝えて?」
と、「外で癇癪しても娘ちゃんにとって何もいい事ないからやらないでね」のニュアンスでトーンを落として話をしていました。
ちなみにここで、

だから!外で癇癪すんなっていつも言ってるでしょ!!なんでわかんないの!?
などと言ってしまうとまた最初からやり直しになる事もあるので(地獄)、
- 感情的にならないこと
- こちらが主導権を握り言いなりにならないこと
は特に気をつけていました。
あとは裏技?でも無いですがうちの娘は癇癪時に言葉が入らない時、ヒソヒソ声で耳元で囁くと「ん?」となりたまに話が入ることがありました。
多分普段あまり聞かない音だから一瞬あれ?となるのかも?
私は買い物が厳しかった時期はよくネットスーパーに助けられてました・・・!!外出しなくてもいいの神・・・
まとめ
というわけで3歳の癇癪対応は、
- 外出する前に「お約束」を伝える
- 出来ないことは出来ないと伝える
- 癇癪の見本を親が見せ危険性を伝える
の3点が主な対応となりました。
3歳のお出かけは今まで抱っこ紐だったのが無くなり自分で歩いてどこまでも行けるようになって、世界が広がった反面守らなきゃいけない社会のルールや公共のマナーなどにも触れる機会が増える時期でした。
そのため「新しいことをやりたい!あれを見たい!触りたい!」など初めて見るもの触れるものに対しての興味ゆえにそれを制されて癇癪につながることもありました。
体が大きくなってくると周りの目が気になるだけではなく、押さえ込んだり抱き抱えたりするのも大変になってきますよね・・・。
外で癇癪が起きてしまうとできることは本当に限られてしまうので、癇癪が起きないように日頃から、
- 外で癇癪しても親は言いなりにならない(子供になんのメリットもない)
- 外の癇癪は危険
- 言葉で伝えた方がいいことがある
ということを繰り返し繰り返し伝えていくことが大事かなと思います。
癇癪に対して一瞬でパッと効果があるものはそうそう無いと思います(大好きなゲーム機とかなら効果があるかもしれませんが多分誤学習してしまうかも・・・)ので、地道ではありますが工程を踏みながら理解を深めていくのがいいかもしれません!(逆に裏技があったら教えてほしいです〜)
今回は癇癪対応(3歳編)を読んでいただきありがとうございます。
よければ4歳編の癇癪対応も読んでいただけると嬉しいです!

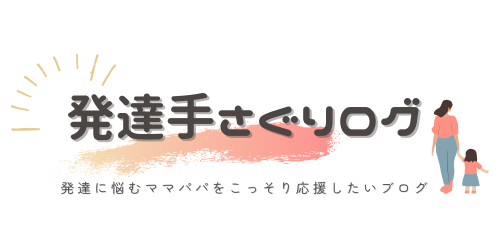
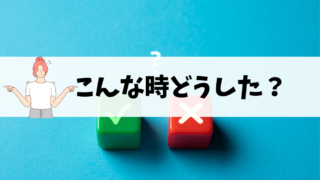
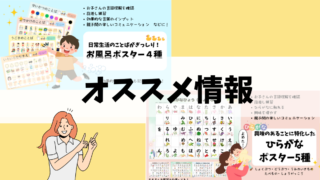

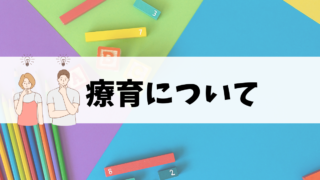




コメント