※この記事は娘の発達歴(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事と併せて見ていただくとどのような発達状態だったかより分かりやすいと思います。
子供って思わぬ怪我をしたり、集団生活が増えると病気になりやすかったりして、病院に通う回数が割と多かったりしますよね。

でも、子供を病院に連れていくのって結構大変です・・よね・・・
病院に連れていく際に持っていく持ち物が多かったり、癇癪や多動があったりすると行く前から絶対大変になることが目に見えてて憂鬱になりますよね・・涙
今回の記事は、発達グレー娘の病院にまつわる記事です。
病院に行く際の娘の様子や実際に取り組んで効果的だったこと、その詳細なども併せてお伝えします。
通院時の大変さに悩む親御さんの病院へのハードルが少しでも下がりますように・・・!!
※子供の病院の苦手さや理由には個人差がありますので、ご参考程度にお願いいたします。
娘が病院に慣れるまで
2歳半頃から病院のハードルが高いと感じるようになる

↑こんな和やかな予防接種は知らないです・・・・
通常の通院の様子
うちの娘は2歳までは基本的に予防接種のみであまり病院に行く機会もなかったのですが、2歳半頃からプレ幼稚園や療育に行くようになり集団の中に少しづつ入っていくようになってから必然的に咳や鼻水などをウイルスから貰ってくるようになりました。
そしてその頃から「抱っこ紐がもう重くて持てない」問題が浮上したことにより、院内では抱っこ紐なしで過ごすようになりました。
2歳半頃は院内が珍しいのと何をされる場所かわかっていないので癇癪はしませんが、椅子に座っていられることもなく院内を早歩きで歩き回ったり椅子の上に寝そべって他のお子さんにジロジロ見られたり、抱っこ紐もないので自由に動けるためお会計中に外に勝手に出て道路に飛び出しそうになることもありました・・・。
そして診察の際に先生の顔を見て「嫌なことをする人だ!(予防注射)」と気づき泣き喚いてガッチリ周りから押さえつけられながら診察する感じではありましたが、癇癪がない分まだ多動な面に気をつけていればそこまでは・・・という感じでした。(病院が近いということもあり)

ただ3歳目前のある日、目を離したすきに家の中で事故が起きてしまいそこから病院嫌いが加速してしまいました・・・。
※外出時の成長遍歴についてはこちら
3歳手前で起きた事故
プレ幼稚園に通ってから数ヶ月すぎ、人や遊びに無関心だった娘もリトミックやごっこ遊びが好きになってきたようで、段ボール箱に入ってバスごっこをよくやるようになっていました。
いつもバスごっこをするときは危なくないようにリビング内で必ず私が見ながら一緒に遊んでいたのですが、その日娘は廊下でバスごっこをしたがりました。
「一緒にそばで見てるから大丈夫かな」と思い娘の近くで何も起きないように見守っていたのですが、廊下に主人のポイントカードが落ちてるのを発見し、拾って主人に届けようと一瞬目を離した隙に「ガッ」と何かがぶつかる音がして娘が「ぎゃあああ!」とすごい声で泣き出しました。
すぐに見に行くと段ボールに入ったままの娘が倒れて部屋の段差に頭を打ち付けたようで泣きじゃくっていました。

ちょっと娘ちゃん!?大丈夫!?
そう言って抱き上げると後頭部には血がべっとりとついており、私もパニック状態に。
夜だったためすぐに救急車を呼び主人と一緒に総合病院に行きそのまま緊急手術となりました。
幸い脳や骨には異常は無く、皮膚が切れただけではあったので医療用のホッチキスでバチンバチンと4針縫っていただき入院する必要も無く帰宅できました。
ただ、暴れないように毛布でグルグル巻きにされた事や麻酔無しで頭を縫われた痛みなどがとても嫌な記憶として残った様子で、この出来事をきっかけに「病院は痛い」「病院は嫌なことをされる場所だ」と娘の中でインプットされてしまった様子でした。(そりゃそうだ・・・)
幼稚園入園後すぐに中耳炎にかかってしまいそれもまた地獄だった
この項目についてはまずこちらの記事を読んでもらえればよりわかりやすいかと思います。(耳鼻科&中耳炎の記事)
幼稚園入園後同年代のお子さんと触れ合うきっかけが劇的に増え、その分鼻水や咳といった風邪の初期症状によく罹るようになりました。
娘は風邪に罹るとすぐに鼻水が垂れ流すくらい大量に出るタイプで、それが完全に取りきれずに悪化し中耳炎になってしまいました。
そして中耳炎の治療は鼻の奥や耳の洗浄が必要になります。かなり繊細な場所ということもあり患者が動かないように渾身の力で押さえつけられることや冷たい機械が鼻や耳の奥に入ってくる不快感や痛みなどもあり娘は耳鼻科が大嫌いになりました。
しかしながら中耳炎の治療はかなり長引き週に3回ほど1ヶ月通院しており私も娘も超ぐったり。

壮絶すぎてもう本当に中耳炎だけはならないでほしい・・・・
高い頻度で嫌な治療を強いられることもあり、耳鼻科だけではなく小児科や歯医者なども含めた病院全体に強い嫌悪感を植え付けてしまう出来事となりました。
というわけで、娘が病院に行くときは決まって「緊急事態」(より症状が重かったり治療が大変だったりする)の時が多かったためそれに伴って楽な治療ではなく、娘にとっても「病院は痛くて苦しい嫌な場所!」と刷り込まれてしまっていました。
それを払拭するのもまた大変でした・・・。
↑記事内でも激推ししている鼻水吸引機です。これで耳鼻科に行かずにすんでます・・・!!
病院に慣れるまでどのような対応をしていた?

病院に慣れさせるまでというのは、
- 「病院に行く」というワードで逃げないこと
- 行く前に癇癪や大泣きをしないこと
- 待合室まで自分で歩いて入れること
- 待合室で迷惑行為をしないこと(泣き叫ぶ、寝そべる、暴れるなど)
- 診察の時に先生の指示に従えること
の上記のポイントが全てできるようになった時点で「病院に慣れた」と判断しました。
そして取り組みを始めたのは3歳3ヶ月頃で上記のことが問題なくできるようになったのは、4歳2ヶ月なので、約11ヶ月程度かかり病院嫌いを克服(?)して行ったことになります。
まずは病院選びから ★★★★★

今まで病院選びは特に意識せずに「近い」「予約が取りやすい」ことを優先して選んでいました。
2歳まではほぼ小児科以外の病院にかかることは無かったですし抱っこ紐で連れて行ったこともあるのでとにかく近くて連れていきやすい場所の病院に行っていました。
ですが、行き慣れた小児科の先生や中耳炎の際にお世話位になった耳鼻科の先生は皆お年を召した先生で『予防注射』『鼻水吸引』『押さえつけられて耳掃除』などの嫌な処置の記憶が蘇るようで、中耳炎の治療が終わった3歳4ヶ月あたりから「おじいちゃんイヤ」というようになりました。
病院以外でもお年を召した男性を見かけると怖がるようになったり、久しぶりに行きつけの小児科に行く用事などがあり行くと先生の顔を見た途端今までよりも強く泣き叫ぶようになりました。

いやああああああ!!おじいちゃんいや!!

(これは・・・おじいちゃん先生は全員嫌なことをしてくると思ってるな・・・!!)
※先生自体はとても優しくていい先生です。あくまでも娘の苦手な印象に入ってしまっただけですのでけしてお年を召されたお医者様を非難しているわけでは全くありませんのでご了承ください。
※癇癪対応についての記事はこちらから
既にイヤな印象ができてしまった病院に通うよりは、新しく娘に会う所を探した方が病院への抵抗感が少なくなるかと思い、下記のポイントに当てはまる新しい病院をいくつかピックアップしていきました。
- 医師や看護師が若い(お年を召してない)
- 子供向け(待合室に子供番組が流れている、キッズスペースあり、子供が騒いでもピリピリしない雰囲気など)
- スーパーが近い(診察終わりのご褒美ルーティーンが作れるため)
- 自転車や歩きで行ける(合う病院なら電車利用も可能)
可能であれば幼稚園が同じママさん達からも子供が行きやすい場所か?キッズスペースがあるか?などの情報も聞いておき、該当する病院を絞っていきました。
病院に行く前に病院のネガティブな面が無いアニメや絵本を見せた ★★★★☆

「病院に行く前」と書きましたが厳密にいうと病院に行く予定の一週間くらい前から日常的に見せていました。
うちの娘はこちらの記事(3〜4歳の発達歴)にも書いたように事前の「お約束」や「見通し」を立てることを徹底しておくと不安感が薄れスムーズに動ける傾向があったため、病院に行く予定がある日の目処が立ったら少し前から「○○日は病院に行くよ」「病院てこんなところだよ」と事前の予告と一緒にアニメを見ました。
アニメの内容は「病院やお医者さんは怖くない」という不安感を薄れさせるものを選びました。
またアニメを一緒に見ている際には、

この子は風邪をひいちゃったから病院に行くんだね

ちょっと心配かもしれないけど、お口をアーンしたりお腹をもしもしするだけなら怖くなさそうだね!
などと
「そんなに病院ってイヤな事しなさそうじゃない?行ってみても大丈夫そうじゃない?」
的なニュアンスで声がけをしながら一緒にアニメを見ました。
もしお子さんの好きなキャラクターが出ている動画などがあればそれを見せてもいいと思います。
おすすめのアニメ

病院はとにかく苦手!怖い!イヤなイメージしかない!お子さんにおすすめ↓
ホッピースマイル:【お医者さんは怖くないよ】
ホッピースマイルの動画は基本的にネガティブな内容や恐怖心を与えるようなストーリーが無くポジティブなストーリーだけを抽出して動画にされているような感じなので、子供に安心感を与えるために見せていました。
風邪をひいて病院に行ったらキッズスペースにおもちゃがたくさんあって遊べて、診察室に入った時ものどを見て胸の音を聞いただけで終わったよ!怖いことは無かったよ!というものです。
まずは病院に対する警戒心を解くために、「病院では何も怖いことはないよ!」という内容のものを選んでも見せるのがおすすめです。

痛くない診察は平気になった!けど注射や吸引は苦手・・・なお子さんにおすすめ↓
しまじろうのわお!:【びょういんなんてこわくない】
↑のしまじろうの動画は注射のお話なので実際に注射をする予定があり、病院への恐怖感がある程度少なくなった状態のお子さんに見せるのがおすすめです。
注射を受けるときにみみりんが「やっぱり怖いからしまじろうも一緒にきて」と言い、予防接種にしまじろうもついて来てくれるお話です。
最初の5分間はみみりん(うさぎのキャラクター)が「予防注射怖いよ〜」と泣く様子が出てくるので、それにちょっと抵抗がある場合は5分以降から見せるといいかもしれません。
病院内で赤ちゃんが泣いたときにしまじろうが手を握って恐怖心を抑えてくれたり、「ここの先生はとっても優しいから大丈夫だよ」「注射なんてすぐに終わるから全然こわくないし、頑張ればご褒美がもらえるんだよ」などと励ましながらみみりんを応援してくれます。
そして実際に注射を打つときも先生が優しい声がけをしてくれたり、注射も全く痛くない描写で描かれていたりと「思ったよりも病院はこわくないぞ」というメッセージ性が含まれています。
なので、「注射ってすぐ終わるんだね」「みみりんを励ますしまじろう優しいね」「◯◯ちゃんの先生も、カバ山先生と同じくらい優しいんだよ」などとポジティブな声がけをしながら見るのをおすすめします。
おすすめの絵本
からだの「なぜ?」絵本シリーズ
体の「なぜ?」にわかりやすく答えてくれる絵本シリーズです。
手を洗う理由、注射をする理由、病院に行く理由などを視覚的に教えてくれます。
出てくるキャラクターがコミカルで読みやすいだけではなく、病院に行く理由や注射をする理由などがしっかりと描かれているので、言葉で「病気にならないために病院へ行かなくちゃいけないんだよ」と説明するよりも子供の納得感が高いと思います。
病院の待ち時間などに持っていって一緒に読んでみるのもおすすめです!
私や主人が通院する際に一緒に来てもらい大人の診察の様子を見せた ★★★☆☆

これについては、病院側に許可をとる必要が出てくるかもしれませんので少しイレギュラーな対応かもしれません。
娘の病院嫌いについては療育先にも「何かいい方法ないですかね?」と相談したことがあり、その際に

他のお子さんの話で、すごく病院に嫌悪感が強い子だったんですが、親御さんが自分の診察がある際には必ず連れていきニコニコでうけている様子を見せ続けていたところ、お子さん自身も診察やお医者さんへの恐怖が薄れていったように見受けられたケースはあります。
と教えていただき、早速私もやってみることに。
とはいえ、娘を診察室に入れるとなるとおそらく側に身内がいないと一人では大人しくしていられない時期だったため、私が風邪をひいたときに主人と一緒に娘もついてきてもらい、診察室の片隅で一緒に様子を見てもらうことにしました。
※病院によっては同行不可(診察室に一緒に入れない)の場合もあると思うのでご確認ください。私は感染症などの流行がない時期にお医者さんに事情を話してOKをいただきました。

はい、では喉と鼻を見ますね〜

は〜い(ニコニコ)

ん〜熱も無いしただの風邪ですね。お薬を出しておきます。お大事に〜

はい、ありがとうございます。(ニコニコ)

あ〜〜〜全然怖く無かったし全然痛くないしあっという間に終わっちゃった〜〜〜
娘ちゃん病院って全然怖く無いみたいだね〜

・・・・・・(泣かずに見てた)
もう完全に「これはただの風邪ひきはじめだし寝てれば速攻治るやつだから診察もきついの無さそう」と確信している軽い症状のときにだけ行きました。
傍目から見てきつそうな診察されそうなとき(耳や鼻掃除のキュイイイイインの機械を出されたりノドの奥に機械突っ込まれてオエってなるやつ)などは絶対に同行させませんでした。
この対応に関しては主人が休日のときにしか行けなかったり病院からNGが出たらそもそも無理な場合もあるので何回もできたわけではありませんが、他人が落ち着いて診察されている様子を見せるのも割と恐怖心や不安感を取るために効果的だったのでは無いかと思います。
小児科などの周りも泣いている子達が多かったりすると自分にも恐怖が伝染してよく泣いてしまっていたのですが、私自身がいく病院は大人しかいなかったのでそもそも泣いている人はいないし、診察中も私がニコニコしながらうけているのを見て「あれ?なんで?病院怖くないの?」みたいな表情で私のことを見ていました。
症状が重く無く問診のみでも問題なさそうな時に積極的に病院に連れて行った ★★★★★

※実はこの項目が最重要項目なんじゃ無いかなと思っています。
そんな感じで下準備を重ねながらついに娘自身が病院に行くことになりました。
というか、「本来なら行かなくてもいい位の症状」の時でしたが「これこそチャンス」だと思って連れて行きました。

連れて行かなくていい位なら行かなくていいんじゃないの?その方がお互いに楽でしょ?

もちろんそれはそうなんですが、軽い問診くらいで終わってくれそうな時に病院に行くことはいくつもメリットがあります!
それは、
- 子供が考えている病院のイメージと齟齬がなくなる
- すぐに診察が終わる&難易度が低いため「病院に行けた!」という成功体験を積みやすい
- 単純に早いうちに病院に行くと症状の悪化を防げ、難易度が高い診察をうけなくて済む
です。
これまでの取り組みでは「病院は怖く無い」「診察は痛く無い」「先生は優しい」というイメージを子供に与えて病院への恐怖心を薄くさせることが目的でした。
そのため、あえて診察の難易度が低い状態で病院に行くことで、

あれ?診察もう終わり?全然痛くないしあっという間に終わった!ママの言う通り病院は怖く無かったし、ちゃんと診察受けられたよー!!
と子供は思うことができるかと思います。
その積み重ねをすることで「病院は怖く無い」と言う気持ちから「病院は体を健康にするために必要なこと」と理解してくれれば少し難易度が高い治療でも最初から「嫌だ!!」と突っぱねるのではなくこちらの説得も聞いてくれるようになるかもしれません。
でも「病院は怖く無い」と言うイメージをしっかりつけておいたにも関わらず、昔の私のように「病院連れて行くのは大変だから本当に必要な時まで連れて行かない」としてしまうと、結局治療も大変なものになりますし、子供も抵抗し先生も鬼の形相になり、

話が違うじゃん!病院は怖く無いし診察も痛く無いって言ってたじゃん!ママの嘘つき!!もう病院いやだ!!
となってしまう可能性が高くなってしまうかもしれません・・・。
もちろん子供を病院に連れて行くのは本当に!!それだけで!!!めちゃくちゃ!!!!大変なことだとは思います。
ですが、症状が悪化してから慣れない病院に連れていって荒治療をされ印象が悪くなってしまうより、症状が軽くて診察や治療の難易度が低いうちに病院に慣れさせる意味で回数を重ねさせるのが、後々親御さんも楽になりますし病院へのハードルを下げる近道なのかなと私は思います。

大変だけど・・・やってみる価値はありました・・・!!
病院帰りには必ずご褒美をあげた ★★★★★

病院帰りのご褒美は恐らくあげている方が多いかと思います。
私は前項でも書いたように、スーパーに近い病院を選んで通院させていたので、

病院に行って、先生のお話を聞いて診察できたら帰りにスーパーで好きなお菓子ひとつ買ってあげるよ!
と娘にとって嬉しいなと思える「お約束」ができました。
もちろん元々小袋のお菓子を持って行き、診察が終わったらそれをあげたりおうちに帰ってからご褒美のおやつを食べるのもすごくいいと思うのですが、病院終わりにスーパーに行けるのこと自体が娘にとっては嬉しかったらしく、また「親が用意したおやつ」ではなく「自分で選んだおやつを買える」こともより楽しかったようです。
なのでそれを繰り返している内に病院に行く時には、

病院でいい子にできたら一緒におやつ買いに行ける?
と聞いてくるようになり、「病院はお菓子を買いに行くための通過点のイベント」みたいな感じで、病院の恐怖よりもその後のイベントにスポットが当たっているような感じになってきました。
また、病院に行けたらすぐにお菓子!だけではなくしっかり言葉で褒めるのも忘れずに繰り返し行いました。

よく泣かないで病院行けたね!先生も「えらいね」って褒めていたよ!これで娘ちゃんの体も健康になったし、病院に行くといいことがたくさんあるね!

おもちゃも絵本もたくさんあるしまた行きたい
あの待合室で動き回ったり泣き叫んだりの地獄の病院通いを経て、「また病院行きたい」と言ってくれるようになるとは・・・・!!
※ABA(応用行動分析学)で「お約束」ができるようになった記事はこちら
もちろん自分にもご褒美を・・何これ美味しそう・・・
まとめ
と言うわけで今回は病院にまつわる記事を書かせていただきました。
娘を病院に慣れさせるために私が行った取り組みは、
- まずは病院選びから(若い先生、近くにスーパーがある、子供向け)
- 病院に行く前に病院のネガティブな面が無いアニメや絵本を見せた
- 私や主人が通院する際に一緒に来てもらい大人の診察の様子を見せた
- 症状が重く無く問診のみでも問題なさそうな時に積極的に病院に連れて行った
- 病院帰りには必ずご褒美をあげた
の5つとなりました。
もちろん大怪我や大変な治療を継続するような病気に罹ってしまった場合はまた特別な対応が必要になってくることもあるかと思いますが、日常的な風邪や定期検診、問診などに関しては上記の方法でもう完全に病院は問題なく行けるようになってきました。
まずは子供にあった病院選びや病院のネガティブさを取り除く工夫を繰り返し、そして軽い症状のときにこそ病院に行って慣れさせる。この方法が娘には良くあっていたのかなと思います。
子供の通院は定型発達のお子さんでも大変だと思いますし、発達不安のあるお子さんであればなお抵抗や不安感が強かったりお医者さんの指示に従うことが難しかったりで、連れて行く側も本当にため息ものの大変なイベントだと思います。
それでも生活して行く中で絶対にいつかお世話になる場所ではあると思うので、少しづつスモールステップで病院へ慣れる取り組みをしていただき、少しでも病院に行く憂鬱が軽くなる方が増えればいいなと思います。
病院嫌いのお子さんをお持ちの皆様本当にお疲れ様です・・・!!宝くじ当たれ・・・・!!
今回は病院にまつわる記事を読んでくださりありがとうございます
よければ他の記事も読んでくださると嬉しいです!!

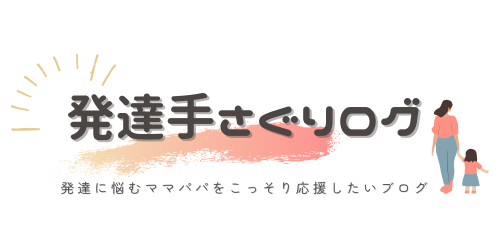
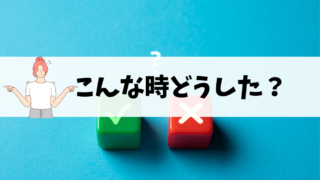
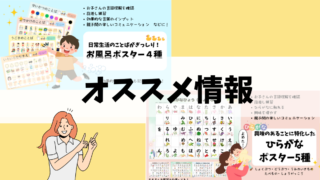

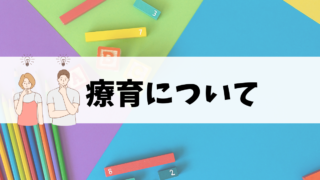

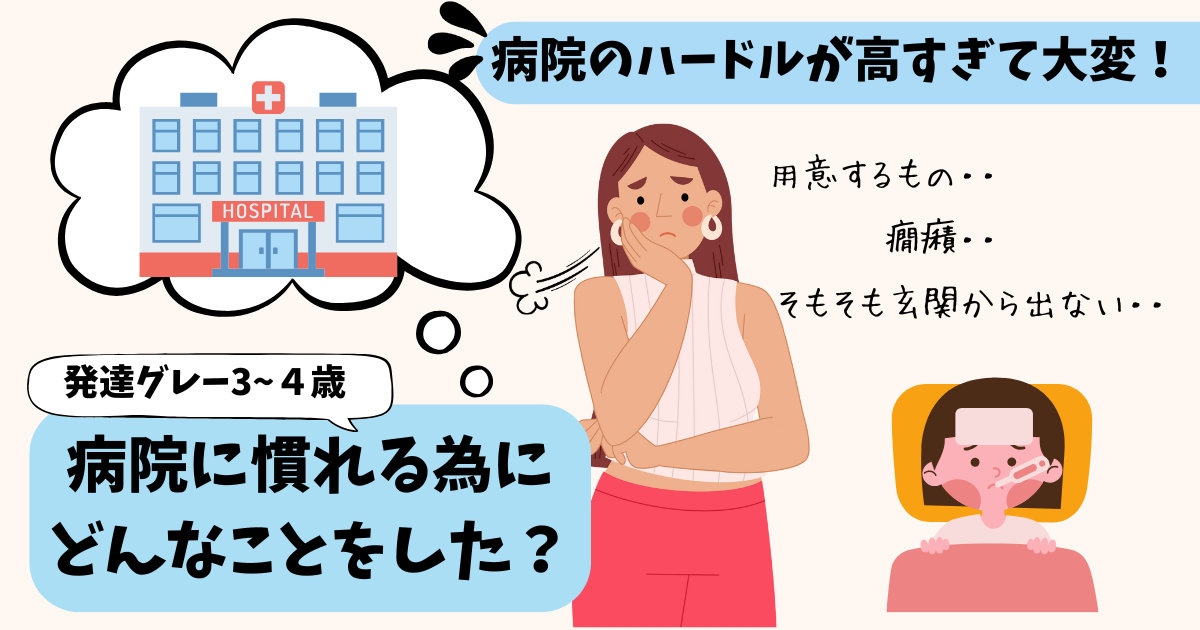
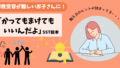
-1-120x68.png)
コメント