この記事では、療育に楽しく通ってもらう為に実際に行った取り組みの中で、より効果的だったものを3つお伝えしようと思います。
※療育を受ける前(0歳〜)や療育を受けてからの発達具合(2歳〜)を詳しく知りたい方はこちら
子供の発達促進や、親のレスパイトや勉強にもなる療育。
2年半通って正直メリットしか感じていないため療育に行ける環境にあるけど行くか悩んでいる親御さんにはそっと背中を押してあげたい私です。
ですが、その場で課題を行うのは子供自身なので、子供が「楽しく」通える環境を作ってあげるのもとても大事なことかなと思っております。

療育の時間は限られているので、できることなら楽しく自発的に行ってもらいたいですよね
療育の基本的な情報や選び方、親目線のメリットなどを知りたい方はこちらからどうぞ↓
子供が楽しく療育に通えるために行った取り組み
子供同士のコミュニケーションを促す

この取り組みを始めたのは療育を始めて割とすぐの2歳半頃からです。
※この時期の娘の発達状態はこちらから
その時期は娘は無発語で他人にも興味がない時期でしたが、興味の幅を広がると発語にもつながりやすいと知った私は、なんとか同じ年代の子供に興味を持つきっかけができないかなぁと考えました。
まずはハイタッチを促した
こちらの記事にも書いてありますが、無発語の場合のコミュニケーションは「ハイタッチ」というツールを使って行うことができます。
ハイタッチは手と手を合わせて音を出すだけの行為ですが、お互いの目を合わせる練習になったり、達成感を味わいやすいため無発語時代頻繁に行っていました。

ハイタッチを療育のお友達ともできるようになれば、お互いに少しづつ意識したり興味を持ったりしてコミュニケーションにつながるかもしれないなぁ
基本ハイタッチは家族や先生とは行ってましたが子供同士でやらせたことはなかった為いい刺激になるかも!と思いやってみることに。
私の場合は集団療育でご一緒しているママさんに以下のような確認をとってから行いました。

○○君のママさん、すみません。もしよかったら通所された際にうちの娘と○○君をハイタッチさせてもらってもいいですか?まだ練習中なんですが・・・

ああ、いいですよ!うちもハイタッチや挨拶の練習になりますし、ぜひやりましょう!

ありがとうございます!!
※触覚過敏や他人とのコミュニケーションに不安感が強いお子さんもいらっしゃるので、コミュニケーションの練習をしたい場合は親御さんに確認をすると安心です。
このような感じで、通所時にお友達がいた際は、

あ!娘ちゃん○○君いたよ!ちょっとハイタッチしてみようか・・あ、そ〜れ

・・・・(ぺち)
のように挨拶ハイタッチを促したり後ろから補助付きでハイタッチをさせたりしていました。
もちろん全然やる気が無くスルーしたりスルーされたりすることも多々ありましたが、お互いハイタッチをしてからお部屋に入室すると、

娘ちゃんと○○君、朝のご挨拶しててすごいね!
と先生がすかさずフォローを入れてくださったりして、そこで初めてお互いの顔を見てみたり様子を観察したり、少しづつお互いを意識しながら課題を行う様子も見られるようになっていきました。
お話ができるようになったら後ろから会話の補助をしてあげる
これは娘が多語文を話せるようになった時期から現在(2025年2月:5歳0ヶ月)まで引き続きやっています。
※この時期の発達状態はこちらから
お話ができるようになると、娘は療育先では色々な人に話しかけるようになりました。
しかし話したいことがまとまってないうちに話し始めたり、頭の中にあることをそのまま口に出したりするので急に言われてもお友達は訳がわからないと言った顔をします。
そんな時に、後ろから会話の補助をするような形で私も会話に加わり、コミュニケーションを促していました。

○○くん、リコがさニャオハに『マジカルリーフ!』って言ったんだよ!

・・・?

娘ちゃん、急に話しかけたらびっくりするかも。あと○○君は「リコ」と「ニャオハ」を知らないのかもしれないよ。
話したことがない内容の時は、まず「ねぇ、○○くんはポケモンのニャオハ知ってる?」とか「ねぇ、ポケモンの話一緒にしてもいい?」とか聞いてみたら?

わかったー。ねぇねぇ○○くんはポケモンのリコとニャオハ知ってる?

ポケモンはなんとなく知ってるけどパウパトの方が好きかも

そっかー!パウパトでは誰が好きなの?わたしマーシャル!

んーと僕はねー・・・・・・(会話が始まる)
こんな感じで、基本は娘たちの会話の様子を見ているのですが言葉に詰まったり表現が難しくて伝えられなかったりした場合は私が間に入り、「こんな感じで伝えてみたらもっと伝わってお話が楽しいかも!」というニュアンスを持たせながら会話の軌道修正を行っていました。
特に、娘は頭に思い浮かんだことをポンと急に話す時が多かったので、療育先での会話の中で少しづつ「前置き」をしてから会話を始めることや一方的に話し続けないことなどを教えていました。
※一方的に話をする時の軌道修正方法についても後日別の記事で書こうと思います。

会話の中で上手に軌道修正が出来た時は、会話終わりに「上手にお話できたね!ちゃんと「ねぇねぇ」って初めに伝えるとお話がしやすいよね!」などとしっかり褒めていました。
いくら語彙が増えてお話ができるようになったとは言え、一方的に話したり頭の中で思っていることを急に話したら相手に伝わらず楽しい会話にはなりません。
このように会話の軌道修正を少しづつ行うことで娘も友達と話をした時に相手に伝わりやすくなったことを実感したようで、私と話をするときも意識的に前置きをしたり一方的に話さないようにするなど、相手の様子を見ながらの会話をしようとしている様子が見られるようになりました!
ごほうびルーティーンを作る

何か頑張った後はご褒美が欲しくなりますよね。それはもちろん子供も一緒だと思います。
療育は遊びの要素が多い場所ではありますが、もちろん着席を促す課題があったり集団だと周りの様子を見ながら取り組むこともあったりして少し緊張したり。
子供にとっては「頑張る場所」でもあるかと思います。
こういう時こそ、ご褒美をしっかりあげて子供のモチベーションをあげるのが大事かなぁと思っています。
ご褒美ルーティーンの例
ちなみに私が行っているご褒美ルーティーンは、
『療育の日は少し早めに行ってコンビニで200円以内の物を一緒に買う』です。
これは今現在も継続して行っています。
やり方はこんな感じ↓
- 療育に向かう前に家で「今日は療育だからコンビニで200円まで欲しいもの買っていいよ」と伝える。(1回目)
- 療育の時間10〜15分前くらいに近くのコンビニへ行く。
- 向かっている途中で

買えるお菓子は100円玉2枚の200円までだよ。欲しい物は決まってる?
と使えるお金と欲しいものの確認をする。(2回目)
- コンビニに入ったら再度「使えるのは200円までね」と伝える。(3回目)
- 欲しいものを見つけたら金額を見て200円以内になっていることを確認する。
※200円以上のものは絶対に買わない - レジに並んで自分で商品を出させ、「これください」と言わせる。
- 買えたら「お約束きちんと守ってお買い物できたね!療育が終わってから家で食べようね」と伝えて療育に向かう。
※このご褒美ルーティーンはABA(応用行動分析学)を参考にして行っています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
↑ABAといえばこの書籍。超超超活用させていただいています!
療育時のご褒美ルーティーンのメリット

療育時にご褒美ルーティーンを作るとこんなメリットがあります!
- 家を出る際に何もない時よりスムーズに出発できる
- 「お約束」をする練習+守るといいことがある と認識させられる
- 買い物の練習になる(お金の使い方・物を選ぶ・順番を待つ・店員さんに敬語を使う)
- 「コンビニでこんなお菓子買ったんだよ!」と療育の先生に自分から話ができる
- 療育終了後帰宅時のぐずりを防ぐ
ご褒美ルーティーンに関しては、週に何回も療育に行っている場合はその内1回だけご褒美を入れるなど、最初に回数を決めてしまうといいかもしれません。
今日はご褒美したけど明日の療育はご褒美なし、などを突然言われると子供にとって「え?なんで?」と不満につながる可能性があるので、ご褒美の日は曖昧にするのではなく、「月曜日の療育の日!」などと決めてしっかり子供に宣言してあげましょう。
または、子供自身に選ばせてもいいと思います。

月曜日・水曜日・金曜日の中で1日だけご褒美にコンビニ行けるけど何曜日にする?
という感じで「行けるのは週1だけ」ということを前提に子供に選んでもらう感じです。
もしかすると、最初のうちは「お約束」をしても

なんで今日はご褒美じゃないの!?コンビニ行けると思ったのに!!
と癇癪されることもあるかもしれませんが、癇癪されたからといって折れて「じゃあ今日もコンビニ行く」としてしまうとお約束の意味がありませんし、「泣けば要求が通る」と誤学習してしまいます。
なので癇癪しても泣かれても折れずに、

ママは来る前に「今日はご褒美の日じゃない」ってちゃんと伝えてるよ。だからご褒美の日以外は買わないよ。
と毅然とした態度で伝えましょう。始めは話を聞いてくれなかったり泣き喚いたりするかもしれませんが(うちもそうでした)、しっかりお約束を伝えているうちに「あ、今日は何を言っても買ってもらえないんだな」ということを少しづつ理解してくるかと思います。
ご褒美ルーティーンで「お約束」を継続して教えていくと外出時の切り替えがすごく楽になります。
誘惑だらけのゲーセンに行って、めちゃくちゃ大好きなゲームをやっていても「ゲームセンターでは1000円まで」と伝えるだけできちんと約束を守って1000円が無くなったら癇癪せずに帰宅してくれたり、逆に1000円でしっかり楽しめるようにするにはどんな使い方をしたらいいのかを考えてくれるようにもなってきました。

ご褒美お菓子を買うと単純に帰宅後に一緒にお菓子で一息つけるのも嬉しい
出来たこと・成長したことを療育施設に共有し、一緒に褒めてもらう

これはもし事業所の方でNGが出なければ是非やってくださいって言いたいぐらいおすすめです!
今は連絡の手段としてLINEやメールを使用されてる事業所さんもあるかと思います。
私は娘が出来たことや成長したなと思った点をLINEに箇条書きでまとめたり、写真で送れるものがあったら送って(ひらがなが書けた、絵が描けたなど)事業所に共有していました。
そして、

すみませんが、娘がこんなことができるようになったので次回通所の際お忙しくなければその点について先生方一緒に褒めていただいてもよろしいでしょうか・・・!
と職員さんの了承をいただいた上でお願いをしていました。
褒められる事によるメリット
心理学では、自分が取った行動に対して良いことが起こると、その行動は繰り返されやすいということが分かっています。逆に、何かをしたことで嫌な結果になった場合、その行動は減っていきます。「褒めると伸びる」では、「良いこと」の部分=「褒め」に当たり、子どもが取った行動に対してしっかりと褒めることで、次も良い行動を繰り返すという導線を作ることができるのです。
また、褒めることは子どもにとって「認められること」であるため、自信をつけさせる効果があります。自分の行動に自信が生まれ、向上心やチャレンジ精神が育まれると言われています。つまり、たくさん子どもを褒めたほうが、健全な育成につながると言えるでしょう。しかし、間違ってはいけないのは、褒めることは「褒め殺しにする」ことではないということです。ただ単に褒めてばかりではデメリットとなるでしょう。
引用:TENJIN から
上記の引用のように適切に褒められることは子供にとって良い事であり、
自信がついたり、チャレンジ精神が生まれたり、自己肯定感が育ったりして新しい事に取り組みやすくなると思います
たくさん褒められる経験をしていると「これもやってみようかな?」「あれもやってみようかな?」と物事に意欲的に挑戦できたり色々な事に興味を持ちやすくなったりするように思います。
※興味を持つことが発達にいい理由はこちらの記事からどうぞ
そのため療育で出される課題が新しくなったり少し難しい物になった時にも意欲的に取り組むことができ、結果的に発達の促進につながることもありました。
療育の先生方に共有して褒めてもらう理由
自分の子供が出来たことや成長したなと思うことを共有して一緒に褒めてもらうのがいい理由は、
- 療育の先生方の褒め方のスキルが高すぎて自己肯定感を上げるのにかなり効果的だから
- 褒め方のバリエーションを間近で見てお家でも活かせるから
- 大人数に褒めてもらう経験は単純に子供のテンションが上がるから
- 子供の発達具合を細かく知ることができるので事業所側も支援計画が考えやすくなる
の4点です。
※4点目は完全にこちらの推測です。
療育の先生方の褒め方について

これほど勉強になるものは・・・・無いぞ・・・・!!
療育の先生方はやはり子供のプロです。褒め方を拝見しているとめちゃくちゃいろんな引き出しを持ってらっしゃることがわかります。
どんな褒め方をされてるかというと、
シンプルに「出来たこと」を認めて褒めてくれる

娘ちゃん、お絵描きで人だけじゃなくてお家や風景も描けるようになったんだね!すごいね!色使いもちゃんと工夫して塗れてるよ!よく観察して見てるんだね〜。
頑張った「過程」を褒めてくれる

娘ちゃんお家や風景が描けるようになったんだね!そっかぁ、ここでも頑張ってたくさん練習してたもんね、先生ちゃんと見てたよ!鉛筆とかクレヨンを使った課題の時も、しっかり紙を押さえてよく見ながら描いてくれるもんね!
「どんな風にやったの?」と深掘りして褒めてくれる

え!娘ちゃんお家や風景が描けるようになったの?すごい!この絵のお家もとっても素敵だけどどんな風に描いたのか先生にも教えてくれない?うんうん、まずは茶色で柱を描いたの?それから赤で屋根をつけたんだ!そうやるとこんなに上手に描けちゃうんだね!先生も今度真似しようかな!
視覚に訴えるように表情豊かに褒めてくれる

えええええ!?娘ちゃん・・・!!お家や風景まで描けるようになったの・・・!?す、凄い・・・!どれ?先生もっと近くで見たいな〜!・・・ええ!これ娘ちゃんが描いたの!?先生素敵すぎてびっくりしちゃったよ・・・!!
もちろん言葉だけではなく表情や身振り手振りなども交えて褒めてくださるので、その様子を見ている娘の中でギュンギュン自己肯定感が上がってる感じが見て取れるんですよね。
また、発達状態や年齢・特性なども加味して褒め方や対応を変えてくださるので、褒められることに依存しがちなお子さんには褒めるよりも共感の言葉を多めにしてみたり、言語理解がまだ浅いお子さんには言葉よりも表情や体全体の表現で「君は凄いね!」ということを伝えるなど、子供によって柔軟に対応を変えられる様子が本当にすごいなぁと思います。
娘は療育の先生方に褒めてもらうと凄くニコニコしながら誇らしげに先生の感想を聞いて、「ここはこんな風に塗った!」「これはこうやったら出来た!」と完全に聞いて聞いてモードになります。
それについても受け止めてくださり、療育が始まる短い時間の中で「しっかり褒めてもらった」体験により、お部屋に入って課題へ向き合うモチベーションが上がったりその日1日の満足度が上がったりしている様子が見られました。

子供の自己肯定感を高めながら感情を引き出す技術というのでしょうか・・・それを近くで見れるのって勉強になりすぎる
大人数に褒めてもらうということ
今の時代、核家族が増えてきていますし、日中はパパかママどちらか一人で子供の対応をされているご家庭も多いと思います。
なので「大人数にワッと褒めてもらう経験」というのを沢山経験しているお子さんてあまり多く無いんじゃ無いかなと思っています。(個人的意見です)
特に発達不安のお子さんや発達障害のお子さんに関しては、親御さんが「褒めよう」と思っても疲弊していて中々褒める気が起きなかったり、周りの目を気にして逆に叱ってしまったりと、褒められる経験が定型発達のお子さんよりも少ない場合もあるかと思います。(個人的意見です)

お世話するだけで精一杯だったりしますよね・・・。ていうか子供より私を褒めてくれと思っていた時期もありましたね・・・それぐらい発達育児は大変ですよね・・・。
ただ、前述したように、適切に褒めてもらったり共感してもらえたりすると子供もテンションが上がりますし単純にとっても嬉しいと思います。
そして親からしても、自分以外の沢山の人に褒められて誇らしげにしている我が子を見るととても嬉しくなります。
療育で沢山の人に褒められた、という経験を基に「今日はお絵描きについて先生に沢山褒められたね!褒められて嬉しそうにしている娘ちゃんを見れてママも嬉しかったよ!」と二重に承認が出来、それが「心地よい」と思ってもらえれば子供自身も「また療育頑張ろう!」と楽しく行けるきっかけになるんじゃ無いかなと思っています。

ただ「出来たこと」だけに注目したり出来なかった時に叱責したりすると「褒められる事」だけに価値があると子供が思ってしまう恐れもあるのでそこは気をつけたほうが良さそうです。
まとめ
というわけで今回は、「療育に楽しく通ってもらうための効果的な取り組み」についてお伝えしました。
まとめると、
- 子供同士のコミュニケーションを促す
(年齢は発達状況で促し方は変えていく) - ごほうびルーティーンを作る
(ご褒美の中の約束事はきちんと守る) - 出来たこと・成長したことを療育施設に共有し、一緒に褒めてもらう
(子供によって褒め方を柔軟に変えてくれるので自己肯定感UPに効果的、その様子も勉強になる)
です。
この3つに関しては、療育を行う上で本当に本当にやってよかったなーと思う取り組みになります。
療育は課題を行うだけではなく親の働きかけによって様々な発達促進の期待ができる場所だと思っています。
もちろん事業所に迷惑になる行為に該当する場合はやるべきでは無いのでしっかり確認を取ってから行うのがいいとは思いますが、おそらく上記の内容で断ってくる事業所さんはあまりないんじゃ無いかと思います。

課題に加えて事業所内でコミュニケーションの練習が出来たり褒められる経験がたっぷり出来たりと、うちの娘にとってはいいことづくめの取り組みでした!やってよかった!
今回は「療育に楽しく通ってもらうための効果的な取り組み」の記事を読んでいただきありがとうございます!どなたかの参考になれば嬉しいです!
よろしければ他の記事も読んでいただけると嬉しいです!

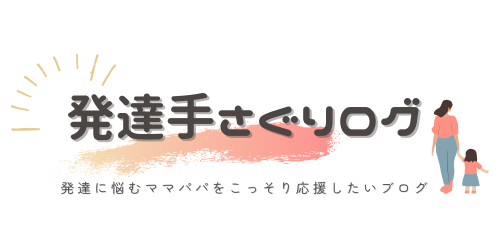
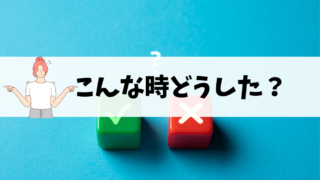
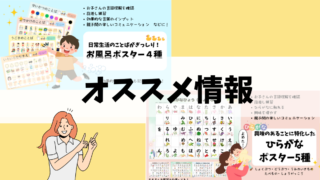

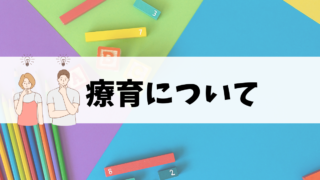


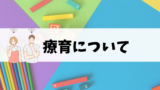



コメント