※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)(4歳〜5歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。
前回の癇癪対応(3歳編)に引き続き、今回は癇癪対応(4歳編)です。
4歳になると、3歳の頃から行っていた「お約束」を大分理解するようになり普段の買い物や日常的な外出の際にはほぼ癇癪も見られなくなってきました。
ただ、ある条件が揃うと激しい癇癪になってしまった事があるので、その点について詳しく記事にしていこうと思います。
娘の癇癪度合いや実際に取り組んで効果的だったこと、その詳細なども併せてお伝えします。
癇癪で悩む親御さんが少しでも楽になりますように・・・・!!
※子供の癇癪の度合いは個人差がありますので、下記のことをすれば誰でも癇癪が治まるといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。
娘の癇癪度合い・スイッチの入り方

3歳の頃は先のことの見通しがつくようになった事で「不安」「上手くいかない」などの要素が加わりそこから癇癪につながる事がありました。
その際は、
- 外出前のお約束を繰り返し伝える
- 出来ないことは出来ないと伝える
- 外での癇癪は危険だと親が見本を見せて教える
などの対応でなるべく癇癪が出ないように、癇癪前対応を心がけていました。
4歳になっても上記のやり方をずっと変えないまま継続しており、日常の中では目立った癇癪は出なくなりました。
しかし、イレギュラーな事が起こってしまった時に大爆発してしまった経験があり、そこから癇癪対応をまたアップデートしていきました。
4歳の頃の娘の癇癪

この頃の私は 会話可能(同年代ではまだ拙いが大人となら問題なし)・自分の嫌な主張が言葉で出来、お約束も理解している・手を繋がなくても隣で歩ける・小さい子は自分より優先できる 状態だったよ!
もっと詳しく発達状況を見たい方はこちらの記事からどうぞ。
◉癇癪の内容
- 年中に進級後初めてのバス登園の際にバスの席が変わって年少さんが窓側に座った時は「自分が窓側がよかったのに!」と泣いて隣の席に座らない。年少さんは悪く無いのに「○○くんが嫌!」と乗車拒否をするようになる
- 家族3人で遊園地に行った際、身長制限がある乗り物に乗りたがり(大人同乗なら乗れる)いざ乗り込む際主人も同乗しようとすると「一人で乗れると思ったのに!一人で乗りたい!」と騒ぎ出し癇癪。「パパと一緒なら乗れる」旨を伝えても泣き止まず着席しないため強制的に降ろされるがそのまま10分程度癇癪。止めようとした主人の腕を強く噛む。
- 療育に行く前にコンビニで小さいお菓子を選んで買うのが習慣の娘。いつものようにお菓子を購入しレジを通り過ぎる時にレジ横のカードゲームを見つけ「やっぱりあっちが良かった・・」と言うもその場を後にする。しかし療育先のドアの前で「やっぱりあっちがよかったのに!!」といきなり癇癪。床に転がる勢いで泣き喚く。
- 集団療育中に一学年上のお友達と勝敗があるゲームをして負けてしまう。「勝ちたかったのに!」とギャン泣きで療育の部屋に入れず私にしがみついたまま15分程度泣き続ける。
内容は割とハードでしたが、4歳〜5歳直前までの約1年間の中で目立った癇癪は恐らく上記の4回のみだと思います。
癇癪が起きたきっかけは、いずれも娘にとって「イレギュラー」な出来事が起こってしまったからだと思っています。
- 園バス癇癪→いつも通り窓際に座れると思っていたが座れなかった
- 遊園地癇癪→一人で乗り物に乗れると思っていたが一人では乗れなかった
- コンビニ癇癪→購入後にもっと欲しい物を見つけてしまったが買えなかった
- 集団療育癇癪→勝敗のあるゲームをすると思っていなかった
上記のコンビニ癇癪などで言えば、本当ならコンビニで買ってもらえなかったその場で癇癪をすることもできたわけですが、その場ではせずに通い慣れた場所に移動してから癇癪を起こしたという点については、娘なりに場所を選んで人目を避けたのかな?と思うところもあり少し場の雰囲気を感じ取れるようになってきたのかな?と思いました。
4歳の頃に行った癇癪対応
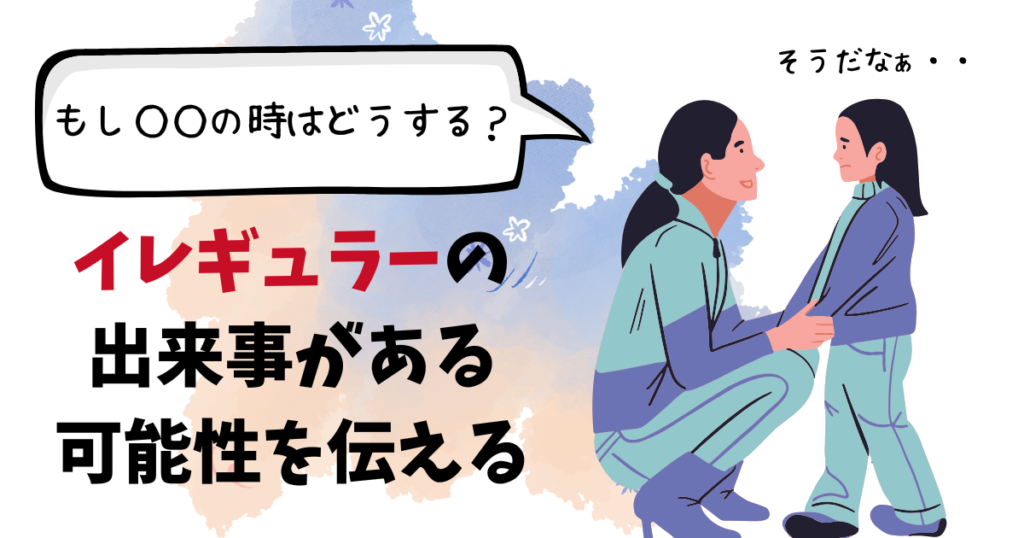
イレギュラーの出来事がある可能性を伝える
前項で記述したようなイレギュラー癇癪が起こった際に「最初から起きる可能性を考えて話しておけば多分癇癪は出なかったのでは?(もしくはそこまでひどくならなかった)」とふと思いました。
4歳になると買い物やお出かけの際の基本的なことについてはお約束でルーティーンができているため、ほぼ問題になることはなくなっていました。
なので、イレギュラー癇癪に対する対応もルーティーン化してしまおうと思い、外出の際は下記のことを行うようにしました。
- 娘に今日の予定を訪ねる「今日はどこに行くんだっけ?」「何をするんだっけ?」
- 娘が「本屋さんで○○の本を買いに行く!」などと答えてくれた場合、「本屋さんに○○の本を買いに行くとするとどんな事が起こるんだろう」と親がまず考える(○○の本が売り切れているかもしれない、近くのクレーンゲームに行きたがるかもしれない、帰りに近くのアイス屋さんでアイスを食べたがるかもしれない など)
- 起こりうる事について「こんな事が起こったらどうする?」と娘に質問していく

もしも○○の本が売り切れて無くなっていたらどうする?△△の本とか□□の本とかにする?それとも買わずに帰る?

え、無かったら?うーんそしたら・・□□の本か他の本を見て決めたいかもー

わかった。○○が売り切れて無くなってても大丈夫そう?

大丈夫だと思う!他の買ってくれるなら!

OK!あったらいいね!でも無くても他の買えるから大丈夫だね!
あと、あそこ近くにクレーンゲーム屋さんがあるんだけどママ小さいお金持ってないから今日はクレーンゲームは無しにしてもいい?それともやりたい?

んー、じゃあ今日はやらなくていいや。いつならできるの?

そっかぁ、わかってくれてありがとう!そしたら今度の休みに大きい駅のゲームセンターで一緒にやろっか!じゃあ今日は本屋さんだけね、それじゃ行こうか!

いくー
のような感じで外出前に問いかけをします。
いつも娘に「○○が無い時はどうする?」などと話しかけると「それは考えてなかった・・!(必ず目当てのものがあると思っている)」のような反応をします。
なので問いかけをせずに実際「◯○が無い」状況に直面すると恐らく気持ちの整理が瞬時につかず癇癪に繋がってしまうと思います。
また、この問いかけを行う事で「今日は○○を買いに本屋さんに行くんだ」という認識が娘の中で強まり、「それ以外はまぁいいや」と他のことに意識が散漫にならずに済むようになりました。
そして実際に「○○が無い」状況に陥った場合も、初めは「えー・・・」と戸惑っていますが、「○○が無い時はどうするって言ってたっけ?」とその場で聞くとハッとして「□□か他の本見るー!」と切り替えがスムーズになりました。
娘にとって「選択肢が○○だけじゃない」「○○が無ければ最悪!ではない」0か100かではなくそれ以外の選択肢を自分で考えることでその結果にも納得して行動ができているように思えました。
好ましくない行動については「いけない」「ママは怒ってる」とハッキリ伝えた

私は基本ABA(応用行動分析学)に沿った対応を基本として娘に接しており、4歳までは99%は褒めて叱るのは1%(というか褒めるべきポイントを無理やり作って無理やり褒めて好ましい行動を強化させていた感じ)という割合でやってきました。
※ABAについて書いている記事はこちら
ただ4歳になると療育のSST(ソーシャルスキルトレーニング)や絵本、私の声かけなどから、善悪の判断や危険な行為、好ましくない行動などがわかってくるようになりました。(やるかやらないかは別)
なのでそろそろやってはいけない行為については「いけない事」「この行動をしたらママはきちんと叱ります」と伝えるようにしました。
ちなみに私が伝えた「いけない行動」とは、
- 危険な行為(道路近くで走る、歯ブラシを加えたまま走ったりふざける など)
- 誰かを傷つける行為(相手は悪くないのに「嫌い」などと言う、腕を噛む など)
- 迷惑をかける行為(公共の乗り物の中で騒ぐ、遊園地で乗り物に乗る直前にゴネる など)
などです。
また、叱り方に関してもいくつかポイントを決めて叱るようにしていました。
- 人目のつかない場所や家の中で叱る(緊急で外出先で叱る場合は人目のつかない場所で叱る)
- 娘の言い分もきちんと聞く
- 聞いた上で、「ママの話も聞いてね、話したいことは○個あるよ」と伝える
- 娘自身は大好きだけど、その行動自体はNGだよと伝える
- いつもより声のトーンは落とすが感情的にはならない
遊園地で思い通りに遊具を使えず主人を噛んでしまった時のことを例にすると、
※人通りの少ない所まで連れてくる

・・・落ち着いた?お話しても大丈夫?

・・・・(頷く)

まず、さっき遊具に乗れなかった時にどうしてあんなにイヤイヤしたのか教えてほしいな、どんな事が嫌だと思った?

・・・一人で乗りたかったの!!なのになんでパパと一緒じゃなきゃダメなの!知らなかったから一人で乗れると思った!!う、うわぁ〜ん(泣く)

そうか、一人で乗れると思ったんだね、だけどパパと一緒じゃないと乗れないってあの場所で言われたから嫌だったんだね、うんうん、確かにいきなり思ってることと違うことを言われたら嫌だよね

嫌だったの!!(泣く)

嫌だったんだね、娘ちゃんの気持ちはわかったよ、ママやパパが先にお店の人に聞いておけば良かったね、それはごめんね。話してくれてありがとうね。

・・・・・・

じゃあ次はママのお話をする番ね、ママは伝えたいことが二つあります、二つ。

一つは、遊園地やお外で遊ぶときはルールを守る必要があると言うこと。
これは娘ちゃんだけじゃなくて皆一緒だよ。誰かが自分の思い通りにしたくて遊具を止めていたら皆使えなくて困ってしまうでしょ?それがもし、娘ちゃんが遊びたい遊具を他の人がイヤイヤして止めていたらどう思う?娘ちゃんは「早く遊びたいのにどうして?」って気持ちにならない?

・・・・なります・・・

皆が皆自分のやりたい通りにしていたら、どこかで「嫌だな」って思う人が出てきてしまうよ、お家の中では自分の思い通りになることが多いけど、たくさんの人の中やお外で遊ぶときは全てが自分の思い通りにならない事もあるという事を覚えておいてね。ただ、ルールを守ればもっと楽しい場所に連れて行ったりしてあげられるからね。

・・・・・(頷く)

もう一つについて、ママは今怒っているよ(声のトーンを落とす)それはパパの腕を噛んでしまった事だよ。

・・・・(泣きそうになる)

嫌な気持ちを持つのは仕方がないことだけど、噛んだり相手を怪我させるような事をするのはいけない事だよ。パパはすごく痛かったと思うよ。ママもパパも娘ちゃんのことはだいすきだけど、噛むことは絶対にしてはいけないこと。これは『お友達や先生ならしないけど家族ならしてもいい』とかじゃない、誰にもしてはいけない事なんだよ。それはわかる?

・・・ごめんなさい・・(泣く)

うん、ごめんなさいが言えてえらいけど、ママじゃなくてパパにごめんなさいしようか

・・・パパ噛んでごめんなさい・・

パパも痛かったし、あんな風に暴れると転んで娘ちゃんも痛い思いをするかもしれないからもうやらないでね
この時は癇癪してから10分後くらいだったので(ずっと背中から抱き締めて落ち着かせていた)だいぶ娘も落ち着き話が通るような状態になっていました。
上記のように、まずは娘の言い分を聞いてあげると娘も「お話をするモード」になり「聞く耳持たないモード」は一旦無くなりやすかったです。
なので親側が色々言いたい気持ちを堪えて先に子供の話を聞いてあげるとこっちの話も聞いてくれるかもしれません。
そして、言いたいことは2つあるよと先に伝えることで娘も集中力を切らすことなく「大事なお話」として聞いてくれているように思えました。
決して怒鳴りつけたりはしませんが声のトーンもしっかり落として真剣モードでお話をすることで、いつもの褒めまくり肯定しまくりの状態からのギャップで「いけない事をしてしまった」と事の重要さに気づいてほしい気持ちもあり、いつもとはガラっと声色を変えてゆっくり伝えていました。
叱っている最中は娘も最初は「叱られている状態が嫌」という感じで泣いたりしていましたが、「パパは凄く痛かったと思うよ」と伝えたあたりで「自分はいけない事をしてしまった」と悟ったような表情からのボロボロっと涙が溢れたような感じで泣いていました。
その日の一連の出来事はとても衝撃的で大変でしたが、反省している様子が見れたことが嬉しく、情緒や他人の気持ちを想像すると言うスキルが少しづつ伸びてきているのかもしれないと思えた出来事でした。
「泣き止んだらお話聞くね」と伝えて待つ
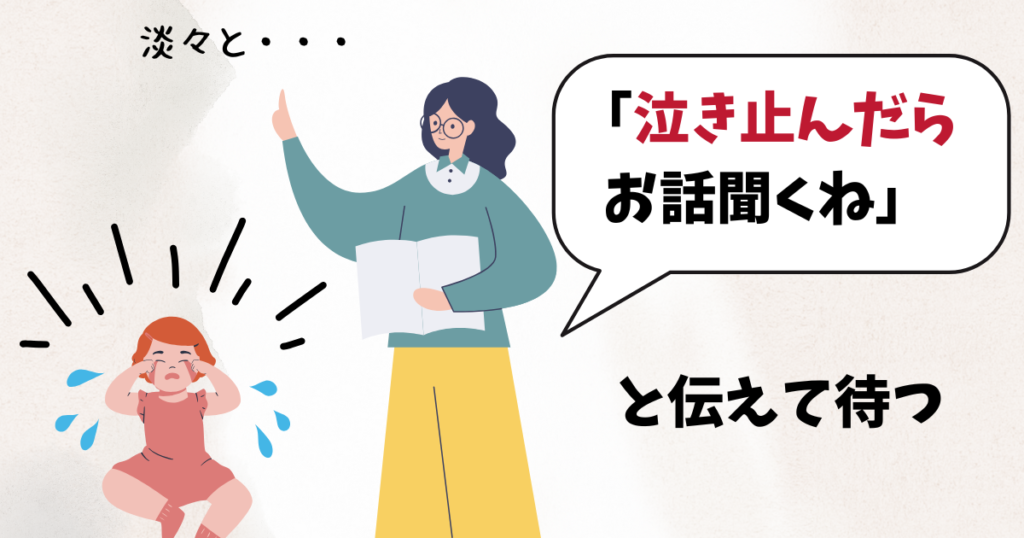
※この対応は外出先では難しいので主に家の中で行っています
この方法は療育先で、娘が4歳になってすぐの頃に先生たちがされていた対応でした。
娘が3歳代の時は泣き出すと先生たちも「どうしたの?」とすぐにお話を聞くモードで対応をしてくれていたのですが、4歳になってからは、

そろそろ「泣いたら先生がきてくれる」状態では無く「泣きやんだらお話を聞いてもらえる」と言う状況に慣れてもらえるようにシフトしていきましょうか
と言われた事もあり、お家でもそのやり方を真似するようにしました。
何か嫌な事があってぐずったり涙が出てしまった時、まずは「どうしたの?何かあった?」とは聞いてみますが声がけでよりぐずりがひどくなる時もあります。
そんな時は、

じゃあママ泣き止んだらお話聞くから、あっちで待ってるね
と言い残しその場を離れます。
泣いていたり気持ちが昂ったりしているのを遠目から少し観察してると、ひとしきり泣いた後で気持ちが落ち着く場面がやってきて、私のところに

泣き止んだ!!(からお話できる!の意)
と報告に来るようになりました。
そしたら、

おぉ!すごいね!自分で自分の気持ちを落ち着かせてママに教えてくれたんだね!ありがとうね!そしたら聞くけど、今は何が嫌だったの?
と気持ちのコントロールを自分でできたことを褒めつつ癇癪の理由を聞いたりします。
「泣いたら話聞く」とだけ言ってその場を離れるだけなのでこの対応は凄く楽で使いやすいなと思いました笑
また、娘自身もひとしきり泣いたりぐずったりして気持ちが発散できている状態で自分から報告に来てくれるので癇癪が起こった理由や内容なども落ち着いて伝えてくれる事が多く、それに対して私が的を得た解答をしやすかったのもあり、その対応に納得して解決するといったパターンが多かったです。
まとめ
と言うわけで、4歳の娘の癇癪対応については、
- イレギュラーの出来事がある可能性をあらかじめ伝えておく
- 好ましくない行動については「いけない」「ママは怒ってる」とハッキリ伝えた
- 「泣き止んだらお話聞くね」を伝える
の3つが主な対応方法ということになります。
4歳になると自分の嫌な気持ちを言葉にして伝えられる事が多くなりましたがイレギュラーで起きてしまった出来事に対する気持ちの整理はまだつけられずに癇癪を起こす傾向があったため、イレギュラーな出来事が起きそうな場合を想定して事前の声がけをすることを重点に置いていました。
ただそれでも起こってしまった癇癪については内容によって「共感」「注意」「しっかり叱る」を使い分けるようになりました。
危険な出来事や他人に迷惑をかけたり傷つける行為についてはそろそろ「本当にやってはいけないこと」としっかり教えておくべきかなという時期に来たのでその点はごまかさずに伝えたり時には「怒っているんだよ」と伝えて事の重要さに気づいてもらうようにしていきました。
ただ、
「いけない」のは好ましくない行動のことなので娘自身を否定したり非難することは絶対にしませんでした。
なので叱るときも「娘ちゃんの事は大好きだけど・・・」を前提に伝えることで「ママは嫌いになってないけどその行動はダメだよ」をわかってもらえるように意識しました。
そのおかげで、癇癪対応をした後でも自己肯定感は損なわれずに自分の行動だけ見直せばいいんだな!と娘も思ってくれたようで割とグズグズ状態からの切り替えも早くなりました!
もうすぐ娘は5歳ということで体も大きくなってきました。これから本気の癇癪をされると止める側の対応も難しくなってくるだろうなぁと思っています。
なのでまずは癇癪が起きる確率を減らすために、お家での事前の声がけや想定できる事をアンテナを張れる範囲内で考えておきいかに癇癪を起こさせないか(もしくは外出先でも解決できる程度に収められるか)が大事なことかなぁと思います。
もちろん今回書いた内容が当てはまらない!という方もいらっしゃるかと思いますが、これならできそう!という取り組めそうなものがもしあれば試していただいて、それがお子様の癇癪の傾向を探るヒントになれば嬉しいなと思います!
今回は癇癪対応(4歳編)を読んでいただきありがとうございます。
よければ2歳編、3歳編の癇癪対応の記事も読んでいただけると嬉しいです!


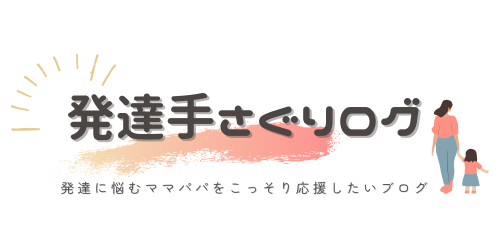
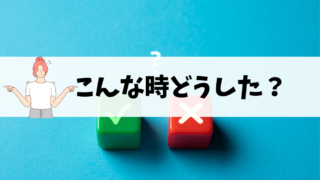
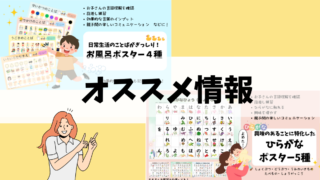

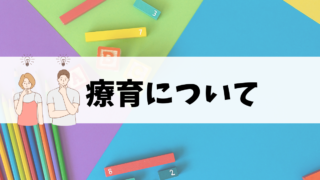



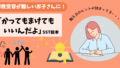
コメント